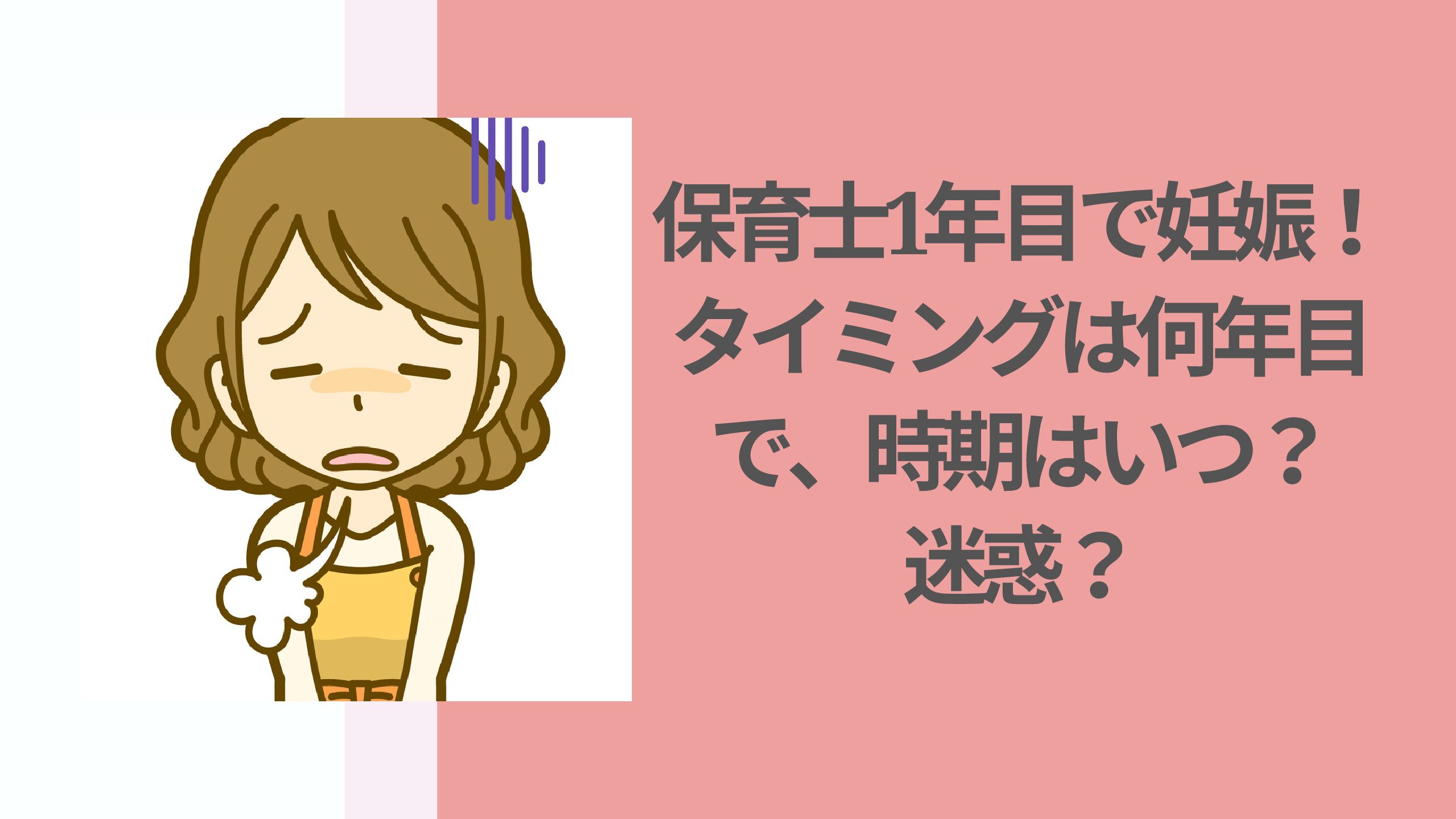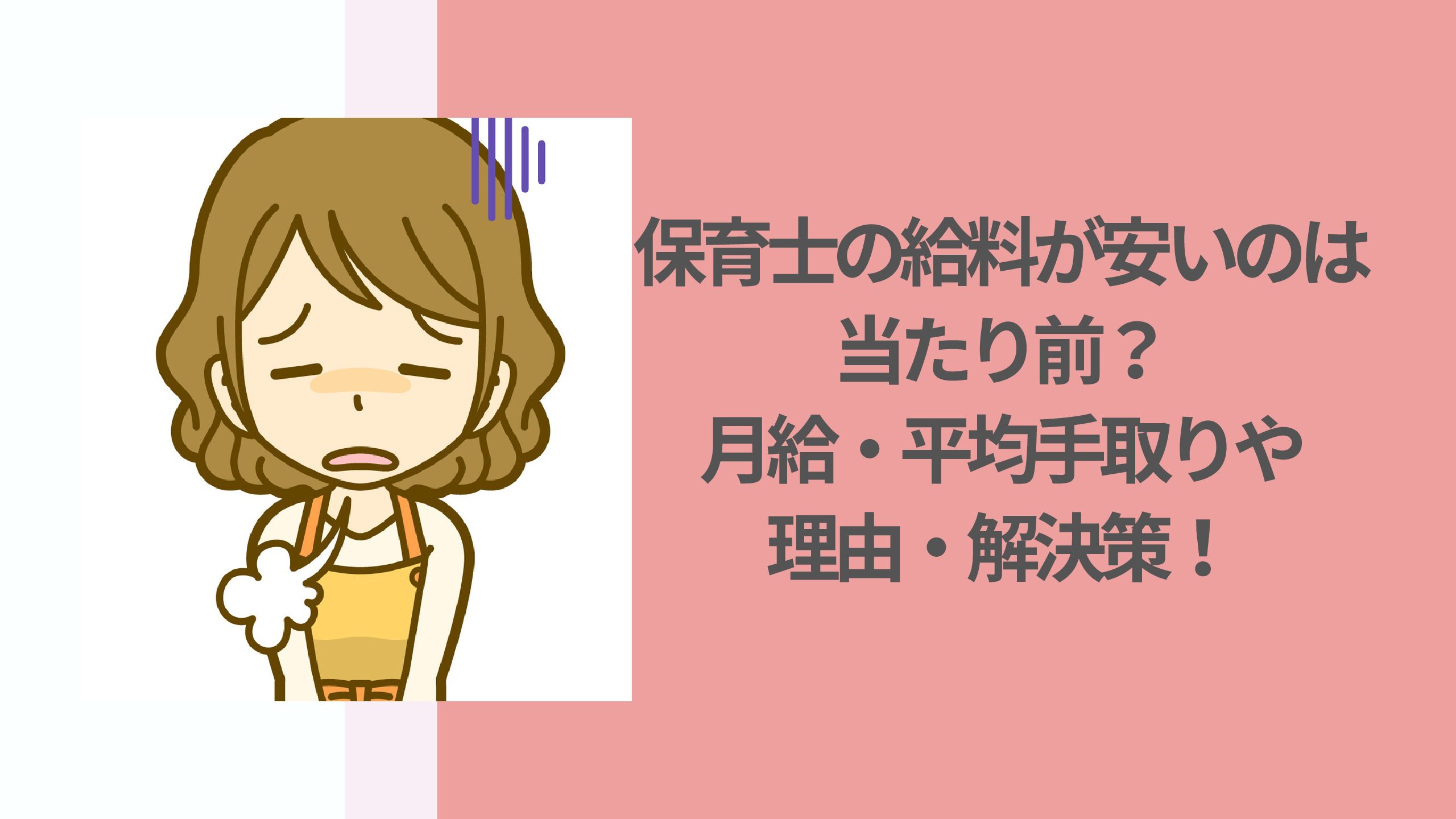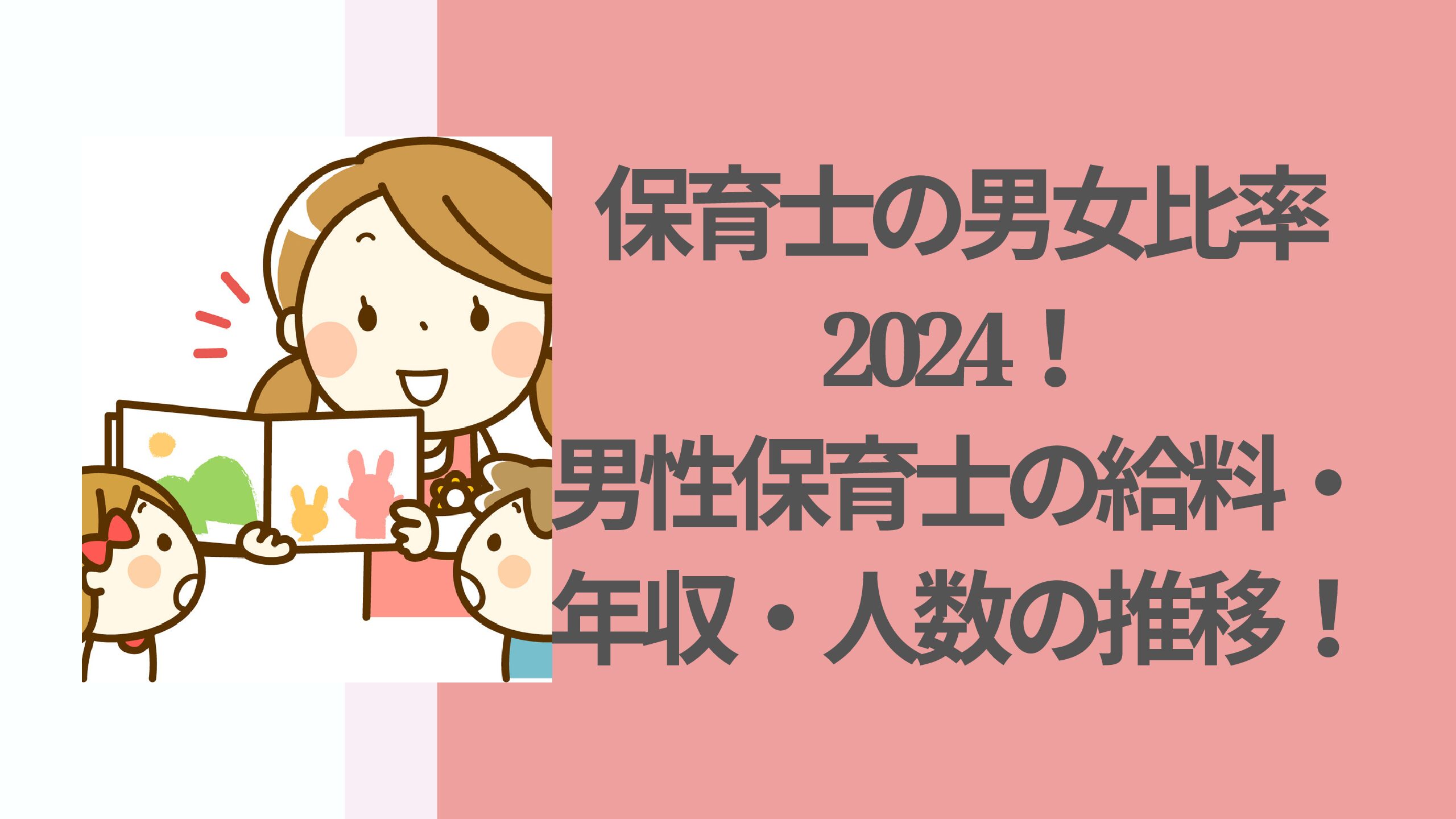PR
厚生労働省の調査によると、保育士の約93%が女性です。
女性が多く活躍する保育士の世界では、保育士の妊娠・出産も珍しくありません。
妊娠は女性の体への負担が大きく、また出産は人生でも大仕事です。
妊娠によって体調が変化することで、保育士の仕事がきつくなり、辞めたいと思うケースも。
今回は、
- 保育士が妊娠により途中退職することができるのか
- 妊娠を機に退職するメリットやデメリット
について、解説します!
保育士を妊娠で退職!
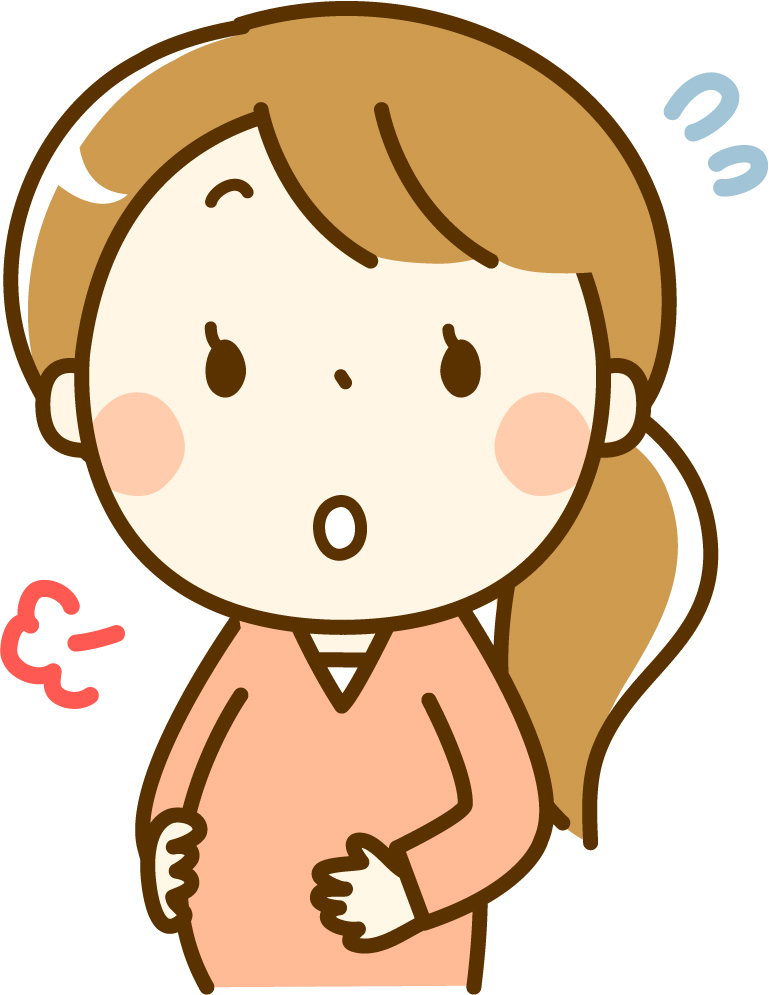
保育士に限らず、女性なら誰でも妊娠が分かった時点で「仕事はどうしよう。」と考えますよね。
- 産休・育休を取り、今の保育園で保育士を続ける人
- 保育士を辞める人
- 今の保育園を辞めて、新しい保育園で働く人
- 産後、落ち着いてからパート保育士や派遣保育士として復帰する人
など、保育士によって様々です。
ただ、妊娠を一つの区切りとして保育園を退職する保育士は、実は多いのです。
実際、妊娠・出産で退職する保育士は、25%以上もいます。
東京都の調査によると、保育士の退職理由の1位は「妊娠・出産」です。
「結婚」という理由も4位に入っていますね。
| 退職理由 | % | |
| 1位 | 妊娠・出産 | 25.7% |
| 2位 | 給料が安い | 25.5% |
| 3位 | 職場の人間関係 | 20.6% |
| 4位 | 結婚 | 20.4% |
*出典:東京都保育士実態調査報告書(東京都福祉保健局)
私自身も、妊娠により退職した経験者です。
妊娠しても、つわりもあまりなく元気な妊婦保育士もいます。
一方で、
- つわりがひどく仕事を休みがちになってしまう
- 抱っこや布団の上げ下ろしで、お腹が張りやすい
- 体調が優れないことで、精神的にも落ち込みやすい
という妊婦保育士も多いのです。
また、妊娠したことで同僚に心配をかけたり、保護者からも「大丈夫ですか?」と言われやすい職業です。
- 周りにあまりにも心配をかけるから
- パートナーも心配するから
- 自分自身が激務についていけないから
など、切実な理由で退職の道を選ぶ保育士もいます。
保育園は、免疫力の低い子どもが大勢集まる場所でもあります。
妊娠中に様々な感染症にかかることで胎児に影響を及ぼすこともあります。
そのような理由で、パートナーや両親に退職を迫られて辞めていった保育士もいました。
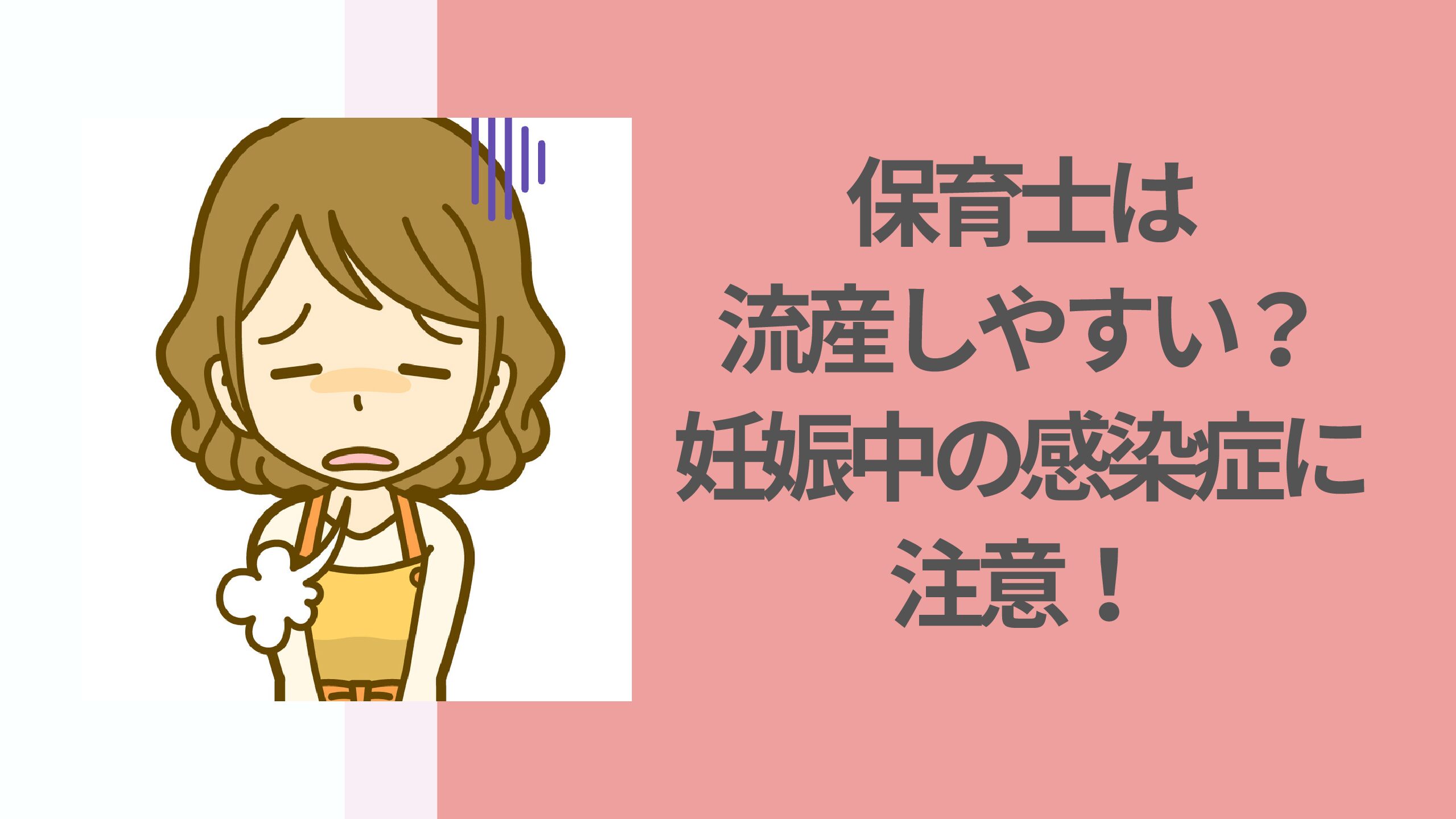

こればかりは人によって状況が違うので、保育士を続けた方がいい!退職した方がいい!どちらも断言はできません。
そこで、妊娠に退職することのそれぞれメリット・デメリットを知っておくことも必要です。
どうすればベストな選択ができるか、考えていきましょう。
保育士は妊娠で年度途中に退職できる?

保育士は妊娠で途中退職できるのでしょうか?
担任を受け持っている場合など、保育士は年度途中では辞めにくいと思ってしまいますよね。
しかし、妊娠中は母体と胎児の健康が最優先です。
妊娠により体調が優れず、ましてや不正出血などあった場合には、自宅安静が必要となります。
保育士が妊娠により途中退職することは、可能です。
実際、退職の時期については、民法で以下のように示されています。
| 【民法 第六百二十七条】
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 |
*出典:民法627条1項
最後の一文にあるように、最低でも2週間前に退職の申し入れをすれば、退職は可能です。
しかし、さすがに退職の2週間前に「辞めたい」と告げると、園から反感を買う恐れもあります。
「サポートするから」などと、引き留めに合う可能性も高いです。
体調の悪い際はお休みをもらいながら、最低でも1ヶ月前には退職の意思を伝えたほうが良いです。
ただし、病気や妊娠など、やむを得ない理由がある際は退職できることも民法では示されています。
民法では以下のように記載されています。
| 【民法 第六百二十八条】
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。 (雇用の更新の推定等) |
*出典:民法628条
こちらは、文中にある通り「やむを得ない事由」がある時に限ります。
急に退職することになった際でも、体調を見ながら引き継ぎノートなど作成し、申し送りに漏れのないようにしましょう。
辞めることができるのは労働者の権利でもあります。
特に妊娠中は無理だけは絶対しないよう、不安な時は産科医に相談しながら考えるのもよいでしょう。
保育士が妊娠で退職するならいつが良い?

妊娠をきっかけに退職することとなった場合、いつ頃辞めるべきかタイミングについても迷いますよね。
- 重度のつわりがあり食事も摂れない
- 不正出血があり自宅安静を指示された
- 動くとお腹の張りが強く出る
などの場合は、タイミングを待っていられませんが、その他の場合はどうなのでしょうか。
同僚にサポートしてもらいながら通常業務ができる場合は、やはり「産休」のタイミングで退職する保育士が多いです。
または、年度末(3月いっぱい)で退職する保育士も多くいます。
産休や年度末まで待てない場合、保育園がある程度落ち着いている下記の時期がよいでしょう。
6〜8月
- 大きな行事が少ない時期
- 新卒保育士も動けるようになってきた時期
- 新入園児も園生活に慣れてきた時期
11〜12月
- 次年度のクラス編成を考え始める時期
- 年明けから求人を始めるために、退職希望者を保育園側が把握したい時期
保育園によって年間計画は異なるため、年間スケジュールを見ながら園長と相談するのもよいでしょう。
新年度が始まったタイミングや運動会などの行事が多い9月〜10月は、保育園全体がバタバタしている時期となります。
無理はいけませんが、体調が安定している場合は、保育園側の都合も考慮しましょう。
保育士が妊娠で退職するメリット
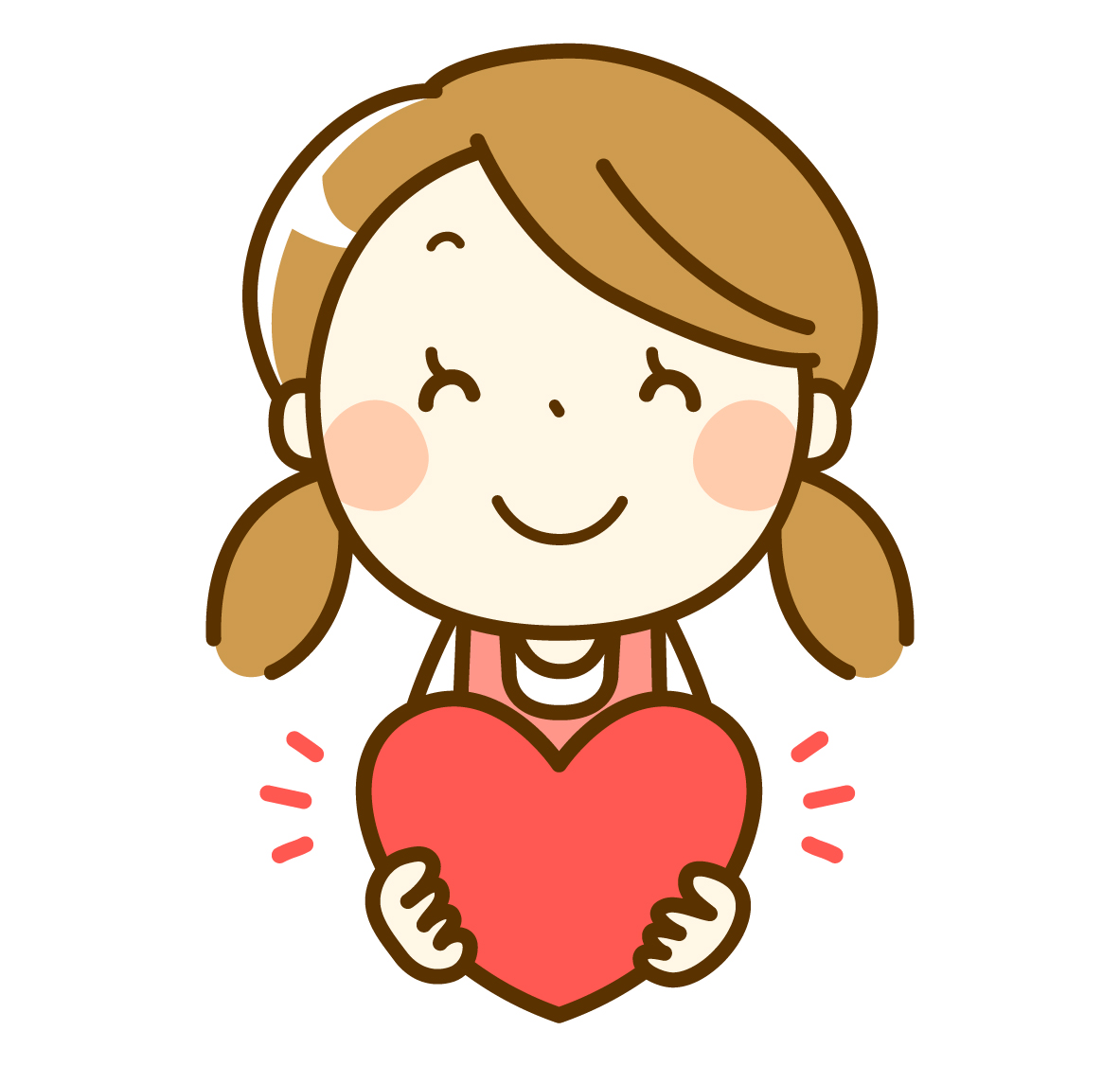
保育士の退職理由の1位が「妊娠・出産」であることは上記でもお話ししました。
妊娠や出産を機に退職する保育士が多いのは、メットもあるからです。
ここでは、保育士が妊娠で退職することのメリットについて解説します。![]()
失業給付金
雇用保険に加入していれば、退職後、次の職場が見つかるまで失業給付金を受け取ることができます。
ただし、自己都合の場合、支給されるまで3カ月ほど待つ場合があります。
妊娠を理由に退職した場合「すぐに求職できるとは言えない」とされ、支給の対象外になります。
しかし「貰えない」と諦めてしまってはもったいないです。
失業給付金は、延長申請をすることができるのです。
最長で3年延長することができます。
すぐには求職できないけど、子育てが落ち着いたら再び働くので、「その時に支給をお願いします」という形です。
受け取る時期を「先延ばしにする」ということが可能なのです。
支給される条件は以下の通りです。
| 離職前の2年間に、11日以上働いた月が12カ月以上ある |
フルタイムで1年以上働いている保育士だけでなく、週3〜4回勤務のパート保育士でも対象となる可能性があります。
また、退職後はほとんどの方がパートナーの被扶養者になることでしょう。
健康保険組合によっては、被扶養者になると失業給付金が支給されないこともあるとのこと。
事前に健康保険組合に聞いたり、出産前に役所に問い合わせをして確認しておきましょう。
また、支給延長を申請する期間は産後2カ月となっています。
すぐに過ぎ去ってしまう期間ですので、産前にしっかり準備しておきたいですね。
産後2ヶ月で自分が動きにくい場合は、パートナーに申請してもらうか郵送で申請するとよいでしょう。
支給の金額については、雇用保険の加入期間によって違ってきます。
退職金
退職するとなれば、まず「退職金」を最初に思い浮かべる方も多いと思います。
勤続年数が長ければ長いほど、退職金の支給額も多くなります。
しかし、退職金が支給される保育園ばかりではないかもしれません。
退職金が支給されても「思っていたより少なかった」という保育士もいるようです。
退職金は、きちんと制度の整っている保育園で勤務しているのなら受け取ることができるものです。
勤続年数が短い場合は、過度に期待しないほうがよいでしょう。
退職するまでに、退職金の制度などを確認しておきましょう。
産前産後の体調ケアが十分できる
産後は昼夜問わずに子育てに追われます。
母乳育児をしている場合、夜間も3時間に授乳しているというママも多いと思います。
私自身も母乳育児の経験者であり、乳腺炎を起こしたこともあって、母乳外来に通いながらの子育てでした。
やはり、時間的に余裕があることで、必要な医療ケアを受けながら安心して子育てできた面は大きかったです。
通院していた母乳外来の助産師さんの話では、「母乳育児をしていると、1日2時間自転車を漕ぐのと同じくらい体力を使う」とのこと。
ゆっくり休むことで、体力的に回復できるのもメリットですね。![]()
子育てに専念できる時間が増える
保育士は、子どもや赤ちゃんが好きな方が多いと思います。
赤ちゃんを見ているだけで、可愛くて仕方ないという保育士もたくさんいました。
そんな可愛い赤ちゃんが我が子だとしたら、やはり片時も離れず一緒にいたいと思うかもしれません。
保育士の場合、赤ちゃんがすぐ泣く、なかなかミルクを飲んでくれないなどのことで大慌てする方も少ないでしょう。
もちろん初産の場合、戸惑うことも多いと思います。
しかし保育士は、全く赤ちゃんに触れずに出産した女性よりは、乳児に対する免疫も知識もあるでしょう。
保育士時代に培った技術を活かして、手作り玩具を作ったり、子どもに弾き語りをしたり、子育てを楽しんでいる方が多いです。
子どもに手がかかる時期は「あっという間に終わる」とも言います。
そんな時期こそ、子育てに専念する!と決めて退職した保育士もいました。
保育士は、共働きで多忙な保護者を保育園でたくさん見ています。
その経験から「自分はゆっくり子どもといたい」と思う気持ちが強くなるのも、自然なことかもしれません。
\ プレママ&ママなら誰でも無料でもらえる!/
Fammプレママ&ママ応援プレゼントキャンペーン
保育士が妊娠で退職した場合のデメリット

保育士が妊娠で退職した場合のデメリットをご紹介します。
夫の収入のみになるため、経済的負担が増える
退職をすると、もちろん「妻の収入」はなくなります。
この件に関しては、妊活中から夫婦でしっかり話し合っている方も多いかもしれません。
ある程度貯蓄をしてから妊活に入った夫婦もいるかと思います。
しかし、そうでない場合、急に減った世帯収入に適応した生活をしなければいけません。
最近では、子育てママもできる在宅ワークも普及し、子どもが寝ている間だけ自宅で内職!なんてママもいます。
また、妻が退職し、子どもを出産することで、パートナーの給料に扶養手当が加算されます。
保育士として働いていた時の収入ほどにはなりませんが、子どもが小さいうちは仕方ないと割り切って考える方もいるようです。![]()
再就職したい場合、認可保育園への入園が困難
子どもが小さいうちは自分で子育てをし、落ち着いてから社会復帰を目指す保育士もいます。
しかし、再就職にあたって注意したいのが、認可保育園に入ることが困難になるということです。
残業も多く、早番や遅番のシフトもある保育士は、認可保育園の保育時間内だけでは対応しきれないことも。
そうなると、早朝や夜間も対応可能な認可外の保育園を利用することになります。
あえて認可外の保育園を探して復職した保育士も実際いました。
しっかりと正社員(正職員)として復職し、保育士としてキャリアアップしたいという方でした。
保育士自体は慢性的に人手不足な職業です。
多少ブランクがあっても求人はたくさんあります。
むしろ、子育て経験者として保護者に安心感を与えるため、保育園側に歓迎されることも。
正社員(正職員)保育士としての復帰以外に、比較的時間帯に柔軟で残業の少ない、
- 派遣保育士
- パート保育士
を選ぶという道もあります。
そして今の生活で、
- 収入
- 保育士としてのキャリアアップ
- 家事、子育てとの両立
のうち、どれを優先したいのか、しっかり考えてから復職の道筋を立てましょう。
産休・育休を取るメリット
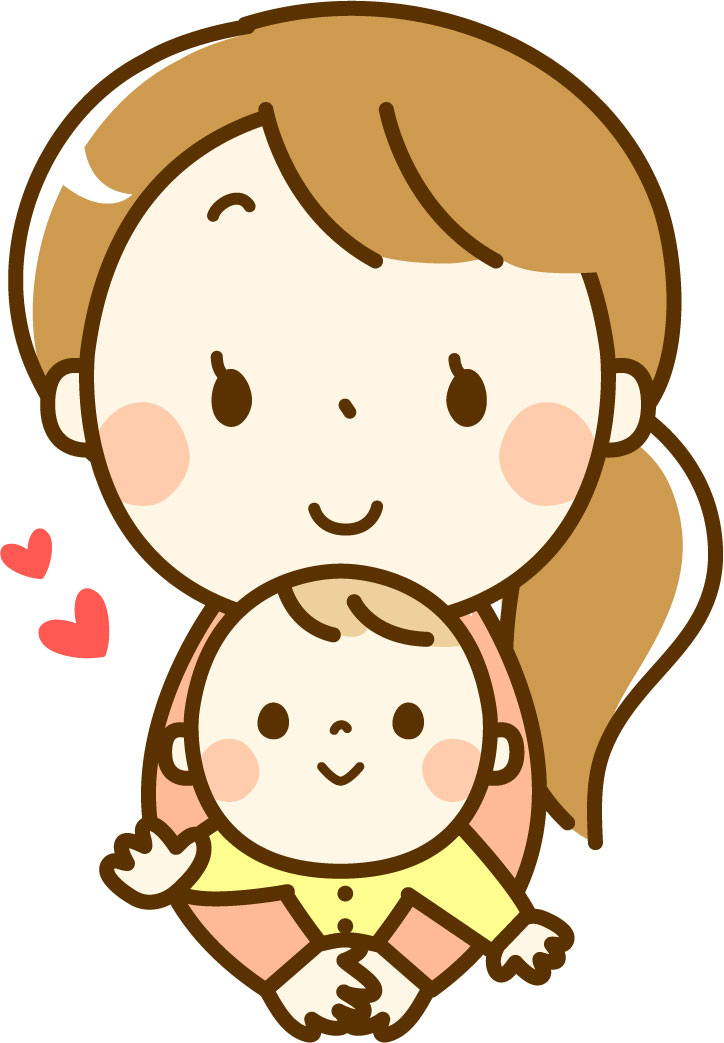
ここまで、保育士が妊娠で退職するメリットを見てきましたが、育休・産休にもメリットがあります。
保育士が妊娠で育休・産休を取るメリットについて具体的に解説します。
育児休業給付金
育児休業給付金とは、労働者が育児休業中に申請することでもらえる給付金のことです。
育児休業中の保育士は仕事ができません。
かといって保育園も休業中の保育士に、今までどおりの給料を支払うわけにもいきません。
育児休業給付金は、育児休業者に国が給付金を支給し、生活に困らないようにするための制度です。
ただし、育児休業給付金の受給には様々な条件や期間が定められています。
国民全員が受給できるわけではありません。
育児休業給付金は通常1歳までしか受け取れる期間はありません。
しかし、平成29年雇用保険制度の改正により、理由があれば、2歳まで延長できるようになりました。
理由があれば2歳まで受け取れる給付金ですが、退職した保育士は対象とならないです。
育児休業給付金の条件の中に「雇用保険に加入していること」という項目があるからです。
雇用保険に加入していないと育児休業給付金は受け取れません。
育児休業給付金はあくまでも「育児休業中の労働者」が対象となる制度です。![]()
社会保険料が免除に
退職をすると、今まで半額保育園が負担してくれていた保険料を自分で払わなくてはいけません。
もちろん、退職と共にパートナーの扶養に入れば必要ありません。
しかし、前述したように扶養に入ってしまうと、失業保険を受け取ることができないケースもあります。
社会保険料や厚生年金の納付額は、前年度の所得によって決まります。
退職した翌年は、少し大きな金額になりますね。
しかも、厚生年金の納付年数が少ないと、老後の蓄えにも影響してくるのです。
社会保険に関しては、退職せずに育児休暇をとる方がメリットが多いのです。
まとめ
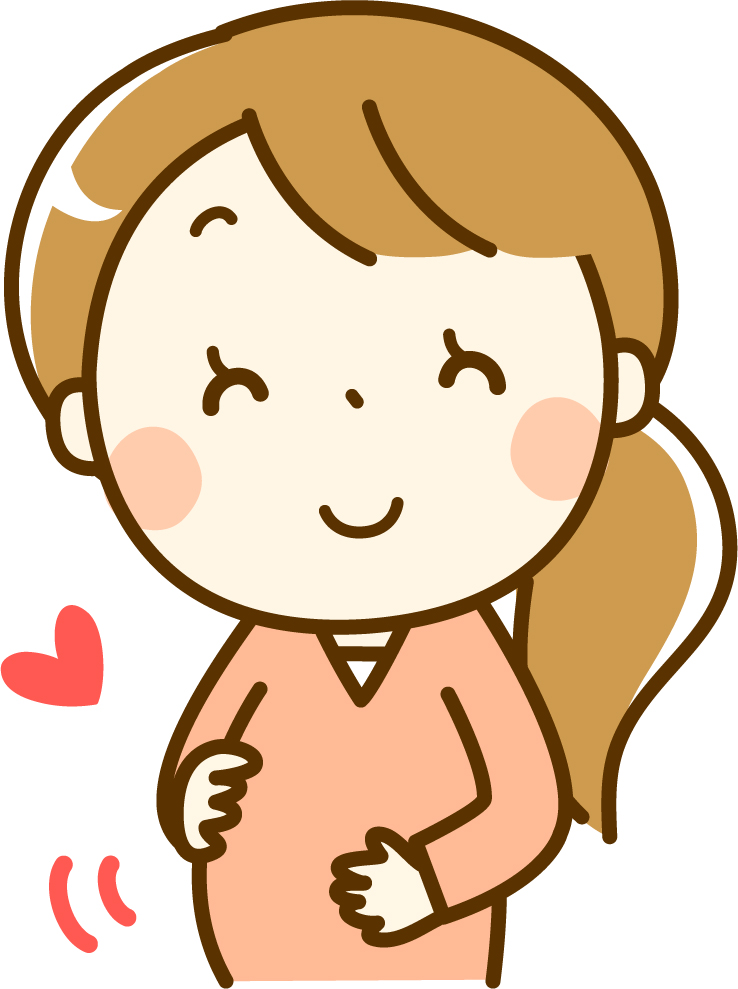
今回は、妊娠によって保育士を途中で辞めることができるのか、解説しました。
退職することを迷っている保育士や、今後出産を希望している保育士の方々に参考になれば幸いです。
妊娠により退職することのメリットやデメリットについても、併せて解説しました。
退職すれば収入がなくなるなどの金銭面の問題は、保育士に限ったことではありません。
しかし、保育士の退職理由の1位が「妊娠・出産」であることを見ると、保育士の仕事がハードである一面もうかがえます。
それ以外にも、やはり保育士は「赤ちゃんとゆっくり過ごしたい」という方が多いのかもしれません。
生活を維持するためにはお金が必要ですが、それ以上にかけがえのない貴重なものもあるのかもしれませんね。