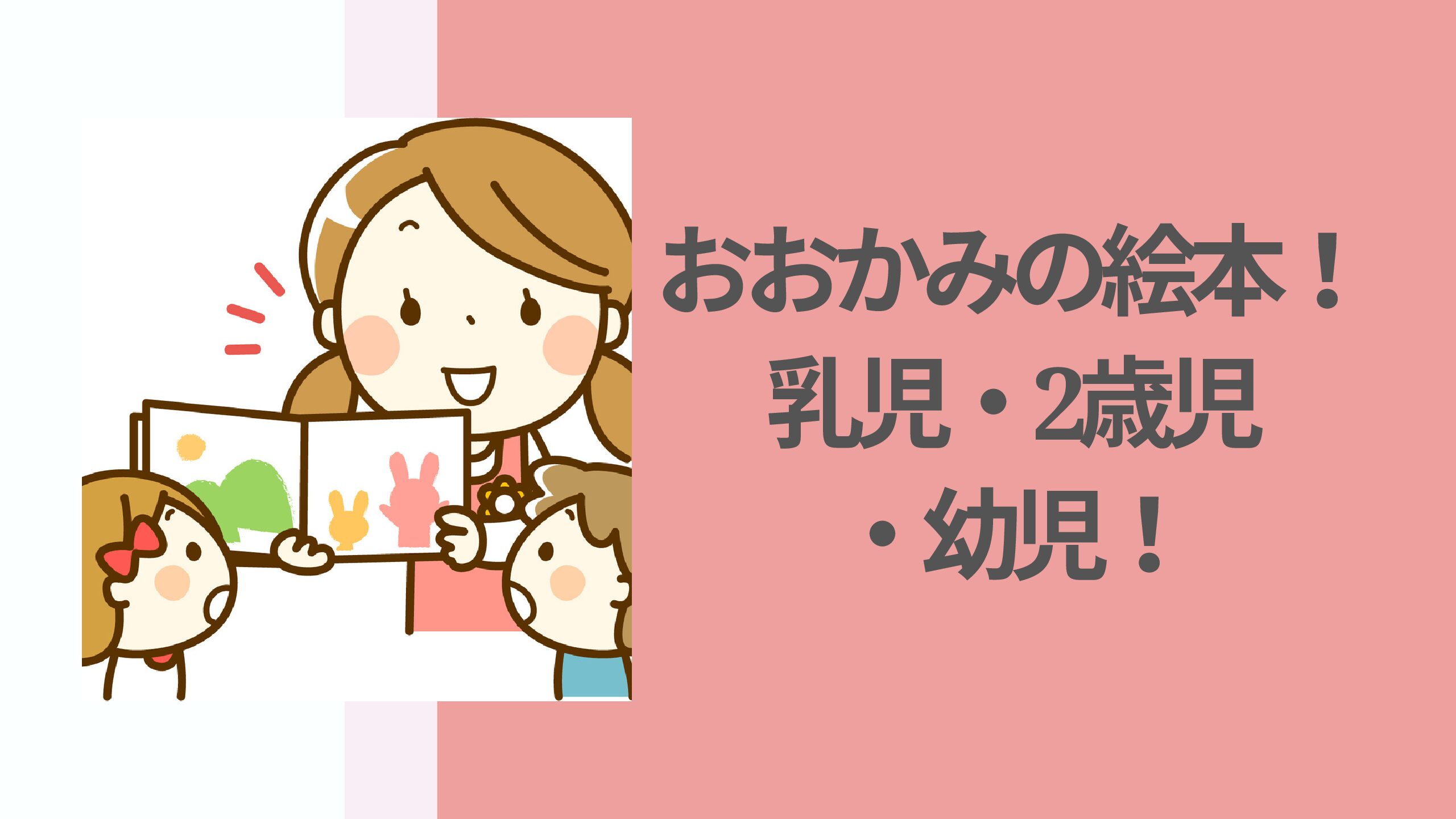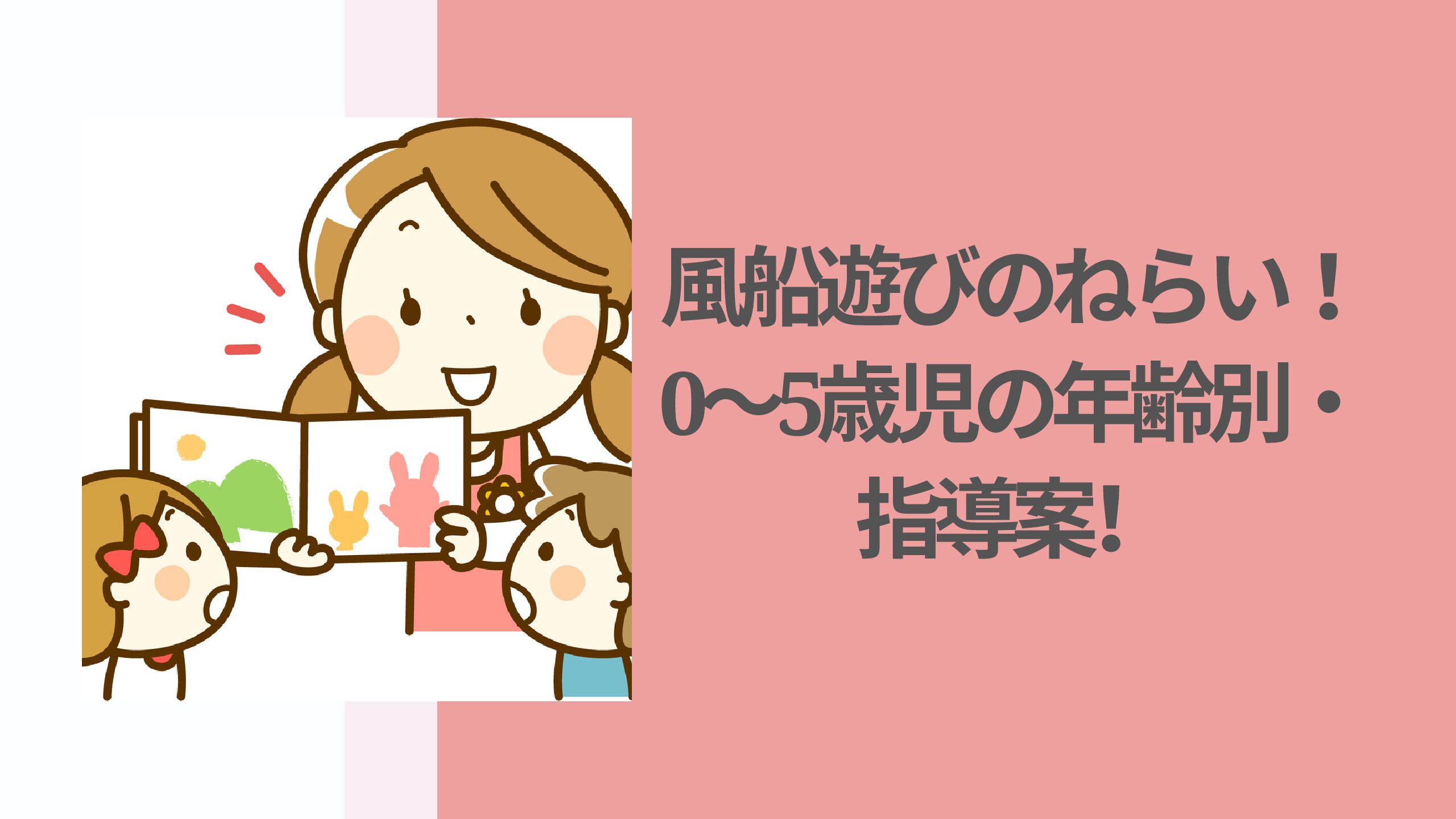PR
毎月の製作や季節ごとの製作、こいのぼりや母の日、父の日などのイベントでの製作など、1年間で行う製作は本当にたくさんありますよね!
今回は数ある政策の技法の中で「ビー玉転がし(コロコロアート)」をご紹介します!
乳児クラスでも先生たちがお手伝いをしたり、ビー玉の扱いに注意したりすれば一緒に楽しむことができます。
私も過去に担任をしたクラスでやったことがあるのですが、なかなか楽しかったですよ♪
ねらいやどんな配慮が必要なのかについてもお話していくので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
ビー玉転がし製作(コロコロアート)のねらい
ビー玉転がし製作(コロコロアート)のねらいをご紹介します。
ビー玉を転がし、画用紙に模様がつく不思議さや面白さを味わう。
ビー玉の動きや線が重なっていく様子を楽しむ。
身近な道具を使って模様を描くことを楽しむ。
学年や目的に合わせて、文言を調整してくださいね!
ビー玉転がし製作ができる年齢
ビー玉転がしは、道具や方法を工夫すれば小さい子でもできる技法です。
過去に担任をした1歳児クラスで行ったときにも、みんな楽しそうに行っていました。
子どもが1人で行うのが難しい時には、一緒に持ってあげることで幅広く楽しむことができます。
2歳児クラスの8月の製作はビー玉を使って絵の具遊びをしました✨
絵の具をつけたビー玉をケースの中に入れた画用紙の上で転がすと、ビー玉の通った道に絵の具が😳
色がついていく様を見て「おー!」と驚きながらも夢中になってビー玉を転がし色がついていく様子を楽しんでいました♪ pic.twitter.com/WTGxntJf7J— 日本初!保育士&看護師専門福利厚生サービスHappeace (@Happeace19) October 15, 2022
ビー玉転がし製作・1歳児
作りたい製作物のサイズにもよりますが、1歳児さんが行う時には、ある程度深さがある箱、もしくは透明でフタがついている箱を使うのがおすすめです。
私が1歳児クラスで実際にやった時の話です。
最初に用意していた箱が浅めだったのですが、まだ力や勢いの加減が上手にできない年齢なので、勢いがつきすぎて何度もビー玉が飛んで行ってしまい大変な思いをしました…。
そこで少し深めなカゴに変更してみた所みんなとっても上手に取り組むことができました!
深めの箱なら、多少勢いがついてもビー玉が転がり落ちてしまうリスクも減らすことができますよね。
子どもたちの中には、なかなか自分で箱が上手に動かせない子もいます。
そんな時には先生が一緒に箱を持ってあげると良いですよ!
また、透明でフタがついている箱、と聞くとあまりピンと来ないかもしれません。
小学生のお道具箱のようなものや、A4サイズなどで売っている書類ケースを想像していただくと良いでしょう。
なぜ透明が良いかというと、中のビー玉の動きが見えたほうが面白いからです!
また、私が1歳児クラスの担任をしていた時に行ったビー玉転がし製作でのねらいは、「ビー玉が転がり模様がつく様子を楽しむ」にしていました。
ビー玉が転がる様子や模様がついていくのを見て楽しんでもらえたら1歳児さんは十分でしょう。
👻おばけ製作👻
0歳児は指スタンプで、1歳児は絵の具の付いたビー玉を転がして、おばけに模様を付けました⭐️
「コロコロ〜」と言いながら転がしたり、ビー玉が転がる様子を目で追いながら楽しそうに製作をしていました😊💕#益子町 #保育園 #製作 #おばけ #ビー玉 #指スタンプ #0歳児 #1歳児 pic.twitter.com/sk4PYCtHNM— 七井保育園 (@nanaihoikuen) August 10, 2022
ビー玉転がし製作・2歳児
1つクラスが上がった2歳児さんでは、先生と一緒によりも、自分で、一人でやりたい!という気持ちが強くなってくるでしょう。
そんな2歳児さんには、最初に先生が簡単な言葉と動きを連動させながら動かし方を見せてあげて、あとは子どもたちに自由にどうぞ!とするのも良いです。
1歳児は、箱を左右にゆらゆら動かす子が多かったのに対して2歳児は、先生の真似をして縦向きや斜めなどいろいろな動かし方にチャレンジできるでしょう。
これを踏まえたうえでねらいを立てるなら、「色々な角度での箱の動かし方を知り、自由に模様を描く」が良いでしょう。
8月の製作をご紹介①🏮
2歳児クラス【ヨーヨー釣り】
ビー玉転がし、マーブリング、プチプチスタンプで模様を作りました✌🏼#8月製作 #ヨーヨー #夏祭り #マーブリング #ビー玉転がし #スタンプ #小規模保育園 #東金町 #金町サニーキッズ保育園 pic.twitter.com/XdfzoMsEXB— 金町サニーキッズ保育園🌞園児募集中 (@SKanamachi) September 8, 2022
ビー玉転がし製作・3歳児
3歳児さんでは、自分で決めた色で模様を描くのがおすすめです。
例えば3色と決められた数の色の中で自由に選び、転がし方も転がす回数や時間も全部お任せにしてみても、案外上手にできるでしょう。
自分で決めて、自由に好きなだけ転がしてできた製作物には愛着もわきますよね。
またゆっくり転がすと太い線、早く転がすと細い線ができることなども、手本を見せてあげれば理解できるでしょう。
「こんな方法もあるよ!」と教えてあげると、より、やりたい気持ちも高まります。
上記の方法で3歳児クラスのねらいを立てるなら、「自分で選んだ色のビー玉を使って、様々な転がし方で線を描くことの楽しさを味わう」良いでしょう。
ビー玉転がし製作・4歳児
4歳児さんでは、一度に転がすビー玉の数を増やしてみると楽しいでしょう。
1つでも不思議な動きをするビー玉ですから、数が増えるともっと面白いことになりそうな予感がしますよね!
「○個までなら自分で数を決めていいよ!」と子どもに伝えます。
- 「自分で決めていいの?じゃあたくさん入れちゃおうかな」
- 「私は3つにしとこうかな」など
お友達と話しながら決めたり自分で考えてみたりする姿が見られるでしょう。
以上を踏まえた4歳児さんのねらいは、「複数のビー玉が様々な方向に転がる様子や線が重なっていく様子を楽しむ」になります。
6月29日 4歳児年中組
ビー玉転がし絵の具をつけたビー玉をコロコロと紙の上で転がしたら、きれいな模様ができあがりました。 pic.twitter.com/CL2fWti9XB
— 港区立芝浦幼稚園 (@shibaurakg) June 29, 2022
ビー玉転がし製作・5歳児
5歳児さんにもなると、自分で色々なことを考えられるようになります。
ここまでで話してきた各学年の発展した技法を取り入れて集大成にしても良いです。
何を作るのかの説明を最初にして、子どもたちに絵の具の色を一緒に考えてもらうのも良いでしょう。
また、実験のような感覚で、ビー玉をつける絵の具の緩さ(水の量)を自分たちで工夫していろいろ試してみるのも面白そいですよ!
5歳児クラスでこの技法をするなら、「作るもののイメージを膨らませながら、色々なビー玉の転がし方を試してみる」がねらいです。
年長組 6月製作「紫陽花」仕上げ
折り紙製作をした紫陽花に、雨を表現するため「ビー玉転がし」を行い、模様付けをしました。 pic.twitter.com/G5xEDiHsGx— sakura-youchien (@Sakurayouchien1) June 21, 2022
ビー玉転がし製作の配慮
ビー玉転がしをする時に最も注意してほしいのが、特に小さいクラスでのビー玉の誤飲です。
丸く小さくキラキラしているビー玉は、飴玉のように見えたりおいしそうに見えて口に入れる可能性があります。
製作を始める前、終わった後には必ず数を数えて個数の確認をしましょう。
また、製作を行っている間は子どもから絶対に目を離さないようにしましょう。
何かがあってからでは遅いので、複数担任の場合は念には念をということで数のダブルチェックをすると安心です。
8月の製作は元気いっぱいのひまわり🌻
ビー玉転がしという作画の技法に挑戦!
豊泉家グループの #企業主導型保育園 のほうせんかキッズクラブ桃山台の玄関には夏らしい元気いっぱいのひまわりが咲き誇っています。#豊泉家 #世代間交流 #保育園 #桃山台 #豊中市 pic.twitter.com/UnXQ3PAfRc— 豊泉家グループ 広報 (@housenka_pr) August 29, 2023
まとめ
小さい子でも先生たちがお手伝いをしてあげたりビー玉の扱いに注意したりすれば一緒に楽しむことができます。
これから行う数々の製作の中で、ビー玉転がし(コロコロアート)という技法も沢山取り入れてみて下さいね!